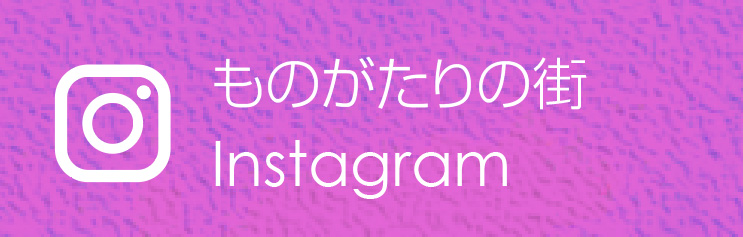私の医療・介護物語
25.05.08
終末期医療の追求から予防を目指す医療へ
《私の医療・介護物語》 第六話-1
ものがたりの街は今年で5年目に入りました。
「思い描く、理想のものができましたか?」という質問をよく受けます。
「いえいえ、ここからが始まりです」といつも答えています。
私はものがたりの街を最期まで暮らしていくためのプラットフォームとして作ったつもりです。
真っ白なキャンパスといって良いかもしれません。携帯電話にアプリをダウンロードして思い思いのものを作るように、ここにいろいろな取り組みをこれから展開していこうと思っています。
人が自然に集まれる場所をこれから作っていくのです。
終末期の医療を15年近くこの街でやって来ました。
そこでは残された時間が少ない方、認知機能の低下している方と初めて出会うのです。今の目の前の状況しかわからない。
そんなところから人間関係を作っていくことに注力して来ました。
私たちは100%死ぬのだから最後に医療と関わるのは必須なことなのです。そこはそれなりの形を作ってきたと自負しています。しかしできれば、もう少し前から、いや病気になる前から、究極には病気にならないような取り組みから、その人の人生の物語を共有する事ができたらどんなに良いだろうか、そう思うようになりました。地域の人ができるだけ病気にならないような取り組みを目指すことを考えます。
病気になってから治すというのは遅すぎます。病気にならないようにしてほしいというのが人類の本当の願いです。
医学という学問はまず人体の正常を学び、次にその異常と治療を学ぶことを使命として発展してきました。
その次のステップとして終末期医療という形で治すことではなく人生の最期、死ぬまでの癒しとしての医療を模索してきた私たちが、今度は病気にならないような社会活動(これも医療といっても良いと思います)というまた別の道を歩んでいくのも必然なのかもしれません。
そのような集団の健康増進や病気の予防(疾病予防)をする学問に公衆衛生学や保健医学というものがあります。
申し訳ないですが、私が学生だった頃(昭和)にもあまり医学部の中では目立つ専門領域ではありませんでしたが、ありました。これからの時代には、その病気にならないための取り組み、集団としての健康という視点が終末期医療とつながっていく発想が大事ではないかと思います。
その時に大事にすることは、やはり「ものがたり」です。他者のものがたりと影響し合うことによって、自他ともが、楽であり楽しい物語であり、苦が少しでも取り除かれていく物語になることを願うものです。
楽を与え苦を取り除く、仏教用語で言うと「慈悲」と言うことかもしれませんね。
「セルフ・コンパッション」と言う言葉もありますがその意味合いがわからないままに言葉だけを使うことにならないようにしましょう(これをプラスティック・ワードと言います)。
終末期医療も予防を目指す医療も、自他のものがたりの幸福や楽を願い、その苦しみを取り除こうとすると言う点では同じだと思います。

月に1度開催する砺波市版認知症カフェ(ほっとなみカフェ)の一コマ
CATEGORY
すべて
ものがたり倶楽部ハウス日記
ものがたりガーデニング日記
ものがたり菜園日記
その他
ENTRY
- 雪の日の贈り物。暖炉を囲む、温かな時間。
- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第10回を開催
- 雪の日に灯る、心あたたまる再会と新春の余韻
- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第9回を開催
- ものがたりの街の花壇の ”冬支度”
CALENDAR
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 1月 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |