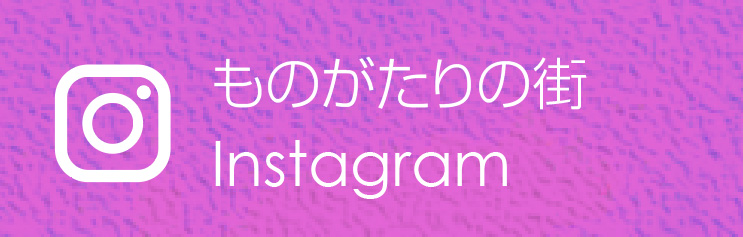私の医療・介護物語
25.02.26
人生の最終章を過ごせる場、医療はものがたりの一部分
《私の医療・介護物語—佐藤伸彦》 第一話
ナラティブホーム
そこには人生の最終章を
家族と伴にゆっくりと
安心して過ごせる空間がある
ただ傍らに在り
温もりを感じ 声なき声を聴け
ただそれだけでいい
ケアの原点は心象の絆の中にある
ナラティブホームは、高齢者が家族と共に最終章を過ごすための場所として2004年に私がその概念を確立しました。
「Narrative Based Medicine」の日本語翻訳が出たのが2001年でしたので、「ナラティブ」はその当時、日本で広く行き渡った言葉ではありませんでした。
2009年に医療法人社団を設立し、翌年にはものがたり診療所を開業し、がんに限らない人生の最終章を過ごす空間「ものがたりの郷」を開設しました。
生命体としての、生物学的な「命」と、ものがたられる人生としての「いのち」とに分けて考え、そのバランスをとりながら「色々あったけどそれなりの人生だった」と思っていただける場、空間を作ってきました。
発想し理念を固め実践まで約10年掛かりましたが、なんとか10年以上続いています。
さてこの、ナラティブという言葉は、厄介な言葉で、その意味を考える前にちょっと日本語についておさらいしておきましょう。
日本語は和語、漢語、外来語、翻訳語の4つからなります。
古来からの和語に漢字が大陸から入ってきて漢語ができます。
明治以降は、発音をそのままカタカナ表記させた外来語(テレビなど)と、漢語を使って新しく作り出した翻訳語があります。
翻訳語は、海外の言葉を表す概念が当時の日本語にないもので、例えば「Society→社会」「Philosophy→哲学」などです。
漢字の「物語」は万葉集に出ていますので翻訳語ではなく昔から使われている言葉で、Story(ストーリー)に相当すると思われます。
さて「narrative」は、日本にその概念が薄かったために、そのまま「ナラティブ」とカタカナ表記で使っています。
語源的にはナレーター、ナレーションと同じで、「語る」「述べる」「説明する」といった動的なイメージの言葉です。
ナラティブケアやナラティブアプローチは、どのような概念でその言葉を使っているのかに注意を払う必要があります。
私は、最近はナラティブという言葉を安易に使わずに、平仮名の「ものがたり」を使っています。
私たちは人それぞれ「ものがたり」があります。生きていること自体がものがたりです。
医療の中に個人の人生があるのではありません。
医療はあくまでも個別のものがたりの一部分です。
人は皆ものがたりを生きているのです。
そこをしっかり見据えた態度が必要と考えて皆さんと日々関わっています。
これから、私の「ものがたり」を少しずつ紐解きながら、人と関わっていくということの意味、難しさなどを考えていこうと思います。
CATEGORY
すべて
ものがたり倶楽部ハウス日記
ものがたりガーデニング日記
ものがたり菜園日記
その他
ENTRY
- 雪の日の贈り物。暖炉を囲む、温かな時間。
- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第10回を開催
- 雪の日に灯る、心あたたまる再会と新春の余韻
- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第9回を開催
- ものがたりの街の花壇の ”冬支度”
CALENDAR
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 1月 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |